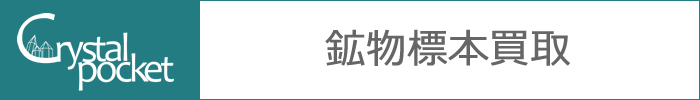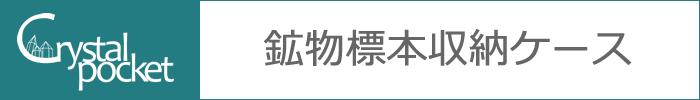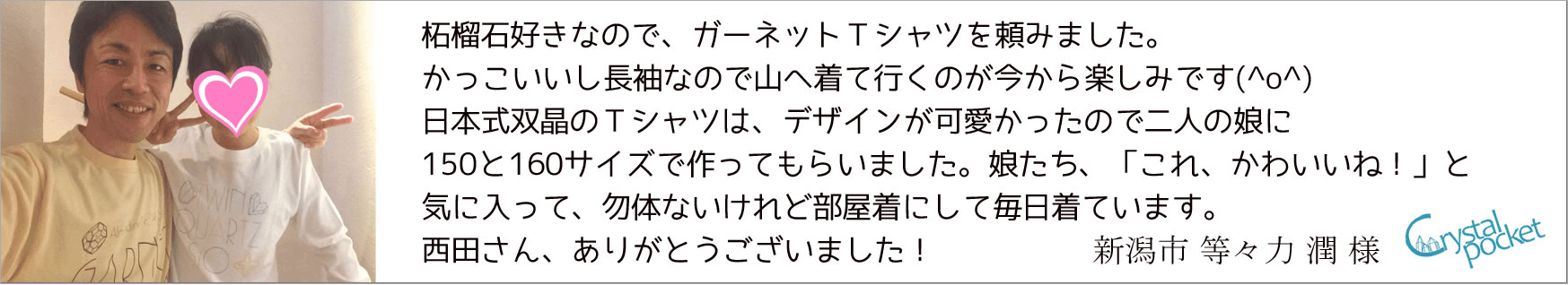鉱物を集める切り口
| 鉱物標本の集める切り口について 鉱物を集めるには自分なりのテーマを決めて集めると、特に楽しいものです。どういった切り口が考えられるのか、考えてみました。 自己標本で構成した益富地学会館の企画展「〇×△□鉱物収集の楽しみ方」もご覧ください。 元素中学の頃にならった元素記号表を思い出してみてください。鉱物はあの元素が結合しあってできたものです。その特定の元素を含むものを中心に集めていくという方法です。元素そのものの姿ではありませんが、単なる2次元の表でしかなかった元素を実際の3次元の姿として見ることができるのが鉱物の魅力のひとつです。元素別の鉱物を調べたいときに役に立つのがこのサイトです。 http://www.mindat.org/index.php 特定の鉱物鉱物の種類によっては、産地ごとに一緒に出る鉱物組み合わせや見かけが異なるものがあります。ベテランになると標本を見るだけで、どこの産地の標本か言い当てることができるほどです。そのためその鉱物種類だけ標本として集めるようにしても、相当に楽しめます。この集め方に向いているのは世界中に産地があり、結晶鉱物であるという鉱物です。水晶(クオーツ)、蛍石(フローライト)、柘榴石(ガーネット)あたりが向いています。世界的水晶産地の例、アーカンソー、ベラクルス、ハーキマー、ダルネゴルスクなど 日本国内の水晶産地の例 玉山、小川山、乙女鉱山、水晶峠、甲武信鉱山、神岡鉱山、田原、白鳥山など 産地別ある産地の中で産出する鉱物を積極的に種類集めをして、ひとつのコーナーとするものです。これは鉱物を学問的に学習したい方に向いています。その産地の中見たときに標本的に立派な鉱物種もあれば、他産地に比べて標本的に貧弱な鉱物種もあったりして、これもかなり楽しめます。こういう集め方をしていると、その産地で多い元素の傾向やでき方のタイプなど気づくことがあります。世界的な産地としてはツメブやモンサンチラール、ミブラーデン、ダルネゴルスク、オハエラなどが鉱物種も多く楽しめます。 日本国内の産地としては、尾太鉱山、田野畑鉱山、秩父鉱山、神岡鉱山、生野鉱山、明延鉱山、石川地方、五良津山、尾平鉱山、木浦鉱山などです。 鉱物種を多く産するということは大規模な鉱床をつくる作用のあった場所で、なおかつ掘り出す作業のなされたところという理由で鉱山が多くなっています。 標本市場では基本的に美的なものや稀産のものを選んで流通していますので、特定産地産として記載されているすべての鉱物種を購入にて手に入れることは不可能に近いと言えます。当然産地を訪れても、産出していた時期や場所などにより、現在では入手不可能な鉱物もありますが、購入のみに比べて、貧弱なものも手に入れることができるので、標本市場での購入に比べて、鉱物の種類に関しては、より多くの種類を手に入れられる可能性が高いと言えます。そして鉱物の鑑定眼を養うという点や産地のタイプを勉強する上でとても意義のあることと言えます。 鉱物の成因別鉱物が生成されるためには、圧力や温度、構成する元素の存在など様々な条件があり、それら条件が整う環境によって、できる鉱物が左右されます。そういった過去に起こった条件を示唆する特徴のある地質現象が見られる場所の代表的なものと代表的な鉱物を挙げてみます。産状が異なっても、生成条件が比較的緩やかであるために、多くの産状で産する鉱物もあれば、生成条件が難しく、世界的に見てその場所でしか産しないものというものもあります。火山ガス噴出場所 温泉湧出場所 溶岩固化物 熱水変質岩 熱水脈 熱水鉱床 花崗岩ペグマタイト 接触変成岩 広域変成岩 海底堆積物 超塩基性岩・正マグマ性鉱床 層状マンガン鉱床 日本の古典標本日本の近代鉱業誌は明治時代から始まります。ダイナマイトや電力を使用した採掘と大資本により採掘規模が飛躍的に増大し鉱物標本が供給されやすい環境が整いました。また西洋から鉱物学が導入されるに伴い、国内の鉱物標本が評価され、保存されることとなったのです。全国各地の旧帝大系の大学には、当時の立派な標本が所蔵されています。 1904年に和田維四郎によって記された「日本鉱物誌」は記載鉱物学の基礎となり、1947年の第3版まで重ねられた「日本鉱物誌」に記載されている産地の標本は古典標本とされ、国産鉱物コレクションのひとつの方向性として重視されています。 鉱物分類別鉱物の分類で同一の系統を集める方法です。化学組成や結晶系、産状などがあります。一般的なのは化学組成に基づく分類です。 元素鉱物(元素単体)、硫化鉱物(硫黄Sと結びついたもの)、酸化鉱物(酸素Oと結びついたもの)、炭酸塩鉱物(炭酸CO3と結びついたもの)、硫酸塩鉱物(硫酸SO4と結びついたもの)ケイ酸塩鉱物(ケイ酸SiO4と結びついたもの)などがあります。 結晶系としては、立方晶系、正方晶系、六方晶系、三方(菱面体)晶系、直方晶系、単斜晶系、三斜晶系といったものがあります。 産状には火山噴出物、熱水鉱脈、ペグマタイト、スカルンといったものがあります。 今回は化学組成分類の硫化鉱物を集めてみました。金属資源として回収されることの多い鉱物です。 元素鉱物 硫・砒化鉱物 ハロゲン化鉱物 酸化鉱物 炭酸塩鉱物 硼酸塩鉱物 硫酸塩鉱物 砒酸塩鉱物 燐酸塩鉱物 珪酸塩鉱物 鉱物の組み合わせ鉱物は複数の鉱物の組み合わせとして産出することも多く、その組み合わせの珍しさや組み合わせならではの美しさを楽しむのも魅力のひとつです。今回は水晶と他の鉱物の組み合わせを紹介しています。水晶(石英)は鉱山の鉱脈として形成されることも多く、他の金属鉱物結晶とコンビネーションを構成しやすい鉱物です。 他にも、長石+トパーズ、長石+雲母、黄銅鉱+閃亜鉛鉱+方鉛鉱、黄鉄鉱+閃亜鉛鉱、黄鉄鉱+黄銅鉱、蛍石+黄鉄鉱、白鉛鉱+青鉛鉱、柘榴石+灰鉄輝石、滑石+透緑閃石、柘榴石+磁鉄鉱など枚挙に暇がありません。 色々な標本を手に入れ、構成している鉱物を書き出してみても面白いと思います。標本として立派でない場合は、ラベルにあえて記述されていない場合もあります。 こういう組み合わせにはこういう鉱物が来やすいという情報を知っているコレクターには、販売者が気づいていない鉱物がついている標本を見つけて安く購入し悦に入るという楽しみもあります(笑 鉱物のさま鉱物のさまの基本要素として、母岩や脈の中に埋没して結晶しているものと晶洞と呼ばれる岩石の中の隙間に結晶するものの2種類あります。この2種類のうち標本として流通していることが多いものは晶洞中のものです。なぜ標本市場で人気があるのかと言えば、晶洞は空間であるため、その中で成長した結晶を色々な角度から楽しみやすく、また透明感のある結晶であれば、色々な方向から入り込む光によって変化する様子を楽しみやすいという要素があります。埋没したものでは、割り出された面からしか楽しむことができず、そういう意味で標本を楽しむ深さが足らない場合があると言えます。それと埋没している結晶の場合は、周りを充填している鉱物によって、結晶面が荒れやすい傾向にあります。ただし鉱物の種類によっては、晶洞中からめったに産出することがない鉱物もあり、そのような場合は母岩や脈の中に埋没した結晶が標本として流通しています。母岩に埋没しているものの代表格のひとつは、造岩鉱物と呼ばれる鉱物標本です。これは名の通り、岩石を構成する鉱物の結晶が大きく美麗になったもので、日本でこの手の鉱物の産地と言えば、太地のSanidine、猪鼻のBiotite、上佐野のdiopside、獅子岩のAugite、信濃境のHornblende、千本峠のβQuartzなどがあります。これらの標本は量的にも多く産するので、鉱物採集入門者に向いた鉱物種です。 それと鉱物のさまについて、結晶面に囲まれた綺麗な結晶に最も人気があるのは当然ですが、ひとつひとつの結晶が微細なものの鉱物が集合し、もこもことした形態を示すものも一定の人気を持っています。 もこもこタイプの結晶をする鉱物の例は、Rhodochrosite、Malachite、Azurite、Fluorite、Calsite、Smithsonite、Prehniteなどがあります。 ルーペで拡大して楽しい鉱物2次鉱物とは、鉱脈や鉱体に生じた金属を含む初生鉱物と呼ばれる硫化鉱物(ZnSなど)が天水により分解し、別の元素と結合し生じるものです。元の鉱物の硫黄分が空気中や天水中の酸素と結びつくことで硫酸が生じ、硫化鉱物を含む岩石の変質を促します。その変質作用が行われている中で、硫黄と離れた金属元素が、酸素や炭酸や硫酸と結びつき、別の鉱物として形成されたもののことです。元の金属鉱物とは全く異なる見かけや色彩を持ち、人気のある鉱物種です。小さなものも多く、ルーペや顕微鏡での観察を行うと色彩や形の豊かな独特の世界が楽しめます。複数の2次鉱物からなるコンビネーションも多く、見飽きない鉱物です。 代表的な2次鉱物 銅 Cu 孔雀石・藍銅鉱(炭酸塩 Cu2CO3(OH)2)、ブロシャン銅鉱(硫酸塩 Cu4SO4(OH)6)コンウォール石(ヒ酸塩 Cu2+5(AsO4)2(OH)4) 鉛 Pb 白鉛鉱(炭酸塩 PbCO3)、硫酸鉛鉱(硫酸塩 PbSO4) 亜鉛 Zn 菱亜鉛鉱(炭酸塩 ZnCO3)大阪石(硫酸塩 Zn4SO4(OH)6・5H2O)アダム石(ヒ酸塩 Zn2(AsO4)(OH)) 鉄 Fe 鉄明礬石(硫酸塩 KFe3(SO4)2(OH)6)スコロド石(ヒ酸塩 Fe(AsO4)・2H2O) |